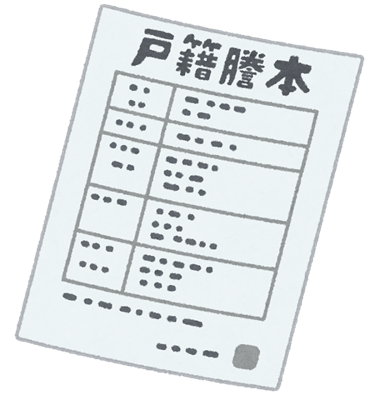十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
四点目は「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。
法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。(日本行政書士会連合会会長談話より引用)
コンサル業務を業として行っておられる非行政書士の方にはインパクト大である可能性が高そうです。
行政書士と提携を希望される方は弊事務所のお問い合わせフォームからお問い合わせいただきますようお願いいたします。